
A Step-by-Step Guide to Implementing Generative AI in Your Business
Please note that this article is currently available in Japanese only. You may use your preferred translation tool while we prepare the English version.
企業の生成AI導入ステップをわかりやすく解説

生成AIの進化により、企業活動における業務の在り方が大きく変わりつつあります。しかし、「何から始めればいいのか」「実際にどのような業務に活用できるのか」「導入にかかる手間やリスクは?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に経営企画部門では、単なる効率化にとどまらず、戦略的な視点からのAI導入が求められています。
本記事では、生成AIの企業導入における活用事例や課題、導入ステップを体系的に整理し、検討の初期段階で知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
企業で進む生成AI導入の現状と背景
なぜ今「生成AI」なのか?
近年、ChatGPTやGeminiなどの登場により、自然言語処理技術を活用した「生成AI」が急速に注目を集めています。
特に企業においては、業務の効率化やコスト削減、新規価値創出の手段としての導入が進んでいます。従来のAIとは異なり、生成AIはテキスト、画像、コードなど多様なアウトプットを柔軟に生み出せる点で、ビジネス活用の幅が広がっています。
生成AIの企業導入率と国内外の動向
国内でも、生成AI導入企業が増加しており、2024年時点で「すでに導入済み」の企業が全体の2割を超えているという調査結果もあります(出典:マクロミル・日経BP「生成AIの活用実態調査 2024」)。
海外ではより導入が進んでおり、ITや広告、製造業、ヘルスケアなど、あらゆる業種で活用が広がっています。先進企業では、生成AIを「業務補助ツール」から「戦略的資産」へと位置づけを変えつつあります。
企業における生成AIの活用シーン

業務効率化・自動化の具体例
生成AIの最も一般的な利用方法は、定型業務の効率化です。
たとえば、カスタマーサポートにおけるチャットボット対応、営業資料や提案書の自動生成、議事録の要約などが挙げられます。これにより、従来人手で行っていた作業の工数を大幅に削減できます。
データ活用と意思決定支援
生成AIは、大量の社内データや公開情報を自然言語で要約・分析し、意思決定を支援する用途でも活用されています。例えば、社内FAQの自動化、顧客の声のトレンド抽出、市場動向のレポート作成などです。
特に経営企画部門では、戦略立案の材料として生成AIを活用する事例も増えています。
生成AI導入の課題と検討ポイント
<

導入に伴う代表的な課題
一方で、生成AIの導入には注意すべき課題もあります。
まず懸念されるのが、情報漏えいやセキュリティリスクです。外部サービスに機密情報を入力する際の管理体制が求められます。
また、社内でのITリテラシーの格差により、誤用や不適切な活用が起きる可能性もあります。加えて、著作権や倫理面での配慮も必要です。
成功するための導入体制づくり
導入にあたっては、まず小規模なPoC(概念実証)から始めることが重要です。
実際に業務でどのように効果を発揮するかを検証しながら、段階的に適用範囲を広げていきます。その際、経営層の理解と現場の協力、IT部門との連携が不可欠です。
また、活用ガイドラインの策定や教育体制の整備も成功の鍵となります。
生成AI導入ステップ
<
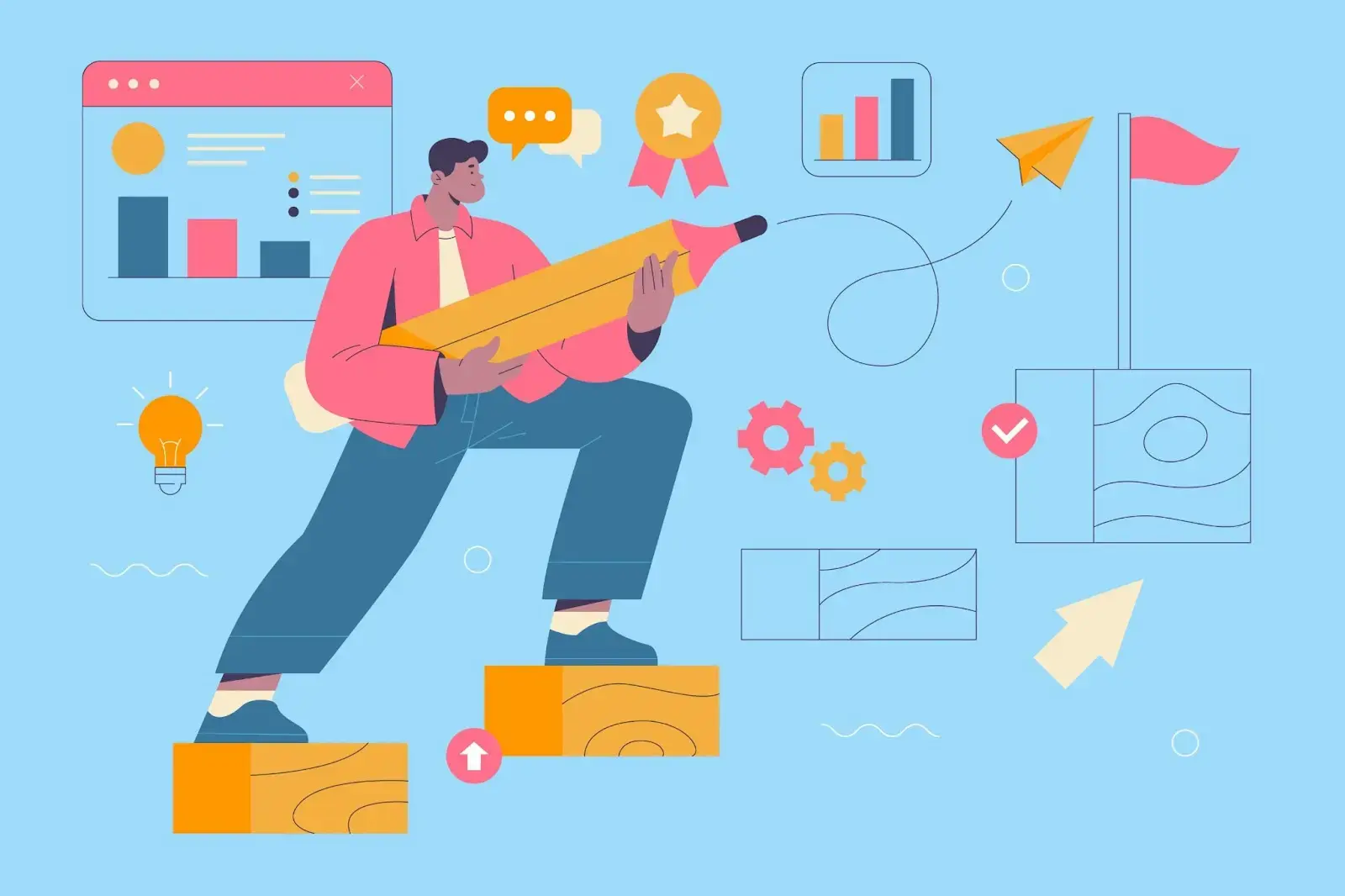
導入の基本ステップ
生成AIを企業に導入するには、以下の5つのステップを段階的に進めていくことが重要です。
ステップ1:導入目的の明確化
生成AIを導入する際には、まず「何のために導入するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。単なるトレンドとしての導入ではなく、自社の課題や業務プロセスの中で、どの部分に生成AIが貢献できるのかを整理します。
たとえば、業務の省力化、ナレッジ活用の高度化、社内コミュニケーションの円滑化など、明確なゴール設定が成功の第一歩となります。ここで目的があいまいだと、ツール選定や効果測定にも支障が出るため注意が必要です。
ステップ2:活用領域の特定とPoCの実施
次に、導入効果が見込める具体的な業務領域を選定し、PoC(概念実証)を実施します。
PoCでは、実際のデータや業務シナリオを使って小規模に生成AIを試行し、実務上の有効性を検証します。例えば、営業資料の作成、社内FAQの自動応答、定型レポートの生成など、影響範囲が限定される業務からスタートするのが効果的です。
PoCの結果をもとに、導入の是非や運用方針の方向性を判断します。
ステップ3:ツール・ベンダーの選定
PoCの結果を受けて、実運用を前提としたツールやベンダーの選定に進みます。
生成AIツールには汎用型のAPIサービスから、業務特化型のソリューションまで多岐にわたります。選定の際は、既存の業務システムとの連携性、セキュリティ要件への対応、操作性、導入実績などを総合的に評価することが求められます。
また、ベンダーのサポート体制や、自社ニーズに応じたカスタマイズ性も選定のポイントとなります。
ステップ4:運用設計・社内展開
導入するツールが決まったら、社内での運用体制を構築し、段階的に展開していきます。
運用設計では、ユーザー管理、利用ルール、エラー発生時の対応フローなどを明文化しておく必要があります。また、利用者への研修やマニュアル整備も並行して進めることで、現場でのスムーズな定着が期待できます。
初期はパイロット部門での展開にとどめ、運用実績や課題をフィードバックしながら、徐々に他部門への拡大を進めるのが現実的です。
ステップ5:効果検証と改善
導入後は、具体的な指標に基づいて効果を検証し、運用の見直しを行います。
たとえば、「業務時間の削減率」「アウトプットの品質向上」「問い合わせ件数の減少」などのKPIを設定し、定量的・定性的な両面から効果を評価します。また、ユーザーの声を拾いながら、ツールの設定調整や追加機能の導入を検討するなど、継続的な改善プロセスも重要です。
単発で終わらせず、社内文化として定着させる視点が求められます。
まとめ|生成AI導入で企業はどう変わるか
生成AIの導入は、単なる業務の効率化にとどまらず、企業の競争力強化や新たなビジネス創出にもつながる可能性を秘めています。経営企画部門としては、戦略的視点で生成AIをどのように活用するかを描きつつ、リスクを管理しながら段階的に導入を進めることが求められます。
まずは、小さく始め、成果を可視化しながら社内全体への展開を目指すことが、成功への第一歩となるでしょう。
DXTimesでは、生成AIの導入やサービスのご案内も行っておりますので、お気軽にお問合せください。





